野生動物
北海道でも酷暑といえる夏となっています。
7月29日に民家のベランダに足跡が発見されたことなどから、北海道とも協議のうえ8月1日にヒグマ注意報を町内の一部地域に発出し、町民に注意喚起を呼びかけました。
平取町では、農作物に被害を及ぼす有害鳥獣(主にエゾシカ、アライグマ、ヒグマ)について、地元猟友会による捕獲活動を行っています。
平取町での年間の捕獲頭数は過去5年間の平均で、エゾシカは2,874頭、アライグマは620頭、ヒグマは31頭となっています。
アライグマやヒグマにはめったに遭遇する機会はありませんが、エゾシカには車道脇や牧場のなか、家の近くにいる姿を頻繁に目にするようになりました。これは、私の記憶ではここ20年くらい前からの現象ではないかと思っています。
職場の役所の周りにも出没します。特に冬は何頭もの群れで、役所の周辺に現れては庭の草などを食べており、奈良公園を彷彿させる光景となることがあります。
農作物への被害が深刻となり、農地には柵を全町的に整備しましたが、個体数としてはそんなに減っていない印象です。現に毎年、平取町だけでも3,000頭近い捕獲をしても減らないという現実があります。日高管内の他の町も当町と同じ状況であると聞いています。アライグマ、ヒグマも同様です。
何故、野生動物が人の生活圏に頻繁に表れるようになったか?この表現は正しくないのかもしれません。もともとの野性動物の生息域を人が支配していったことを考えると、本来の自然の領域が復活してきているのかとも思ってしまいます。
当町にも縁の深い野性生物の保護管理問題に詳しい、東北芸術工科大学の田口洋美教授によると、この要因について「以前は中山間地域は集落、耕地、里山、奥山といった空間配列、いわゆるゾーニングが必然的に成り立っており、野生生物を奥山へと押し上げていた圧力があったが、人口減少、若者流出などによってゾーニングが崩壊し、圧力が下がり野性動物の防衛ラインが決壊した。」ことが大きいということです。うなずけるところがあります。人口減少、高齢化はこのようなところにも影響を与えていることが伺えます。
いずれにしても、野生動物等による人的被害が生じることは回避しなければなりません。町も猟友会や警察、関係者の皆様と連携し、被害の回避に最大限努力してまいります。
町民の皆様には、早朝や夜の外出等、生ごみの管理等には十分留意されることをお願いします。また、夏休みの期間はさまざまな行事などが予定されていると思いますが、子どもたちの送迎等についてご配慮をお願いいたします。
暦の上では秋とはいえ、まだまだ暑い日が続くと思われます。体調管理に留意されお過ごし下さい。




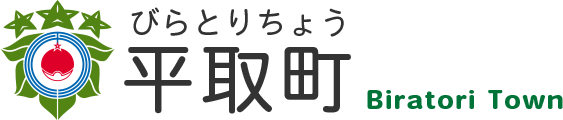


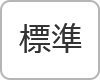
更新日:2025年08月14日
公開日:2025年08月14日